ゼミナールの選び方
商学部ゼミファイル

 2024
Vol.1
2024
Vol.1
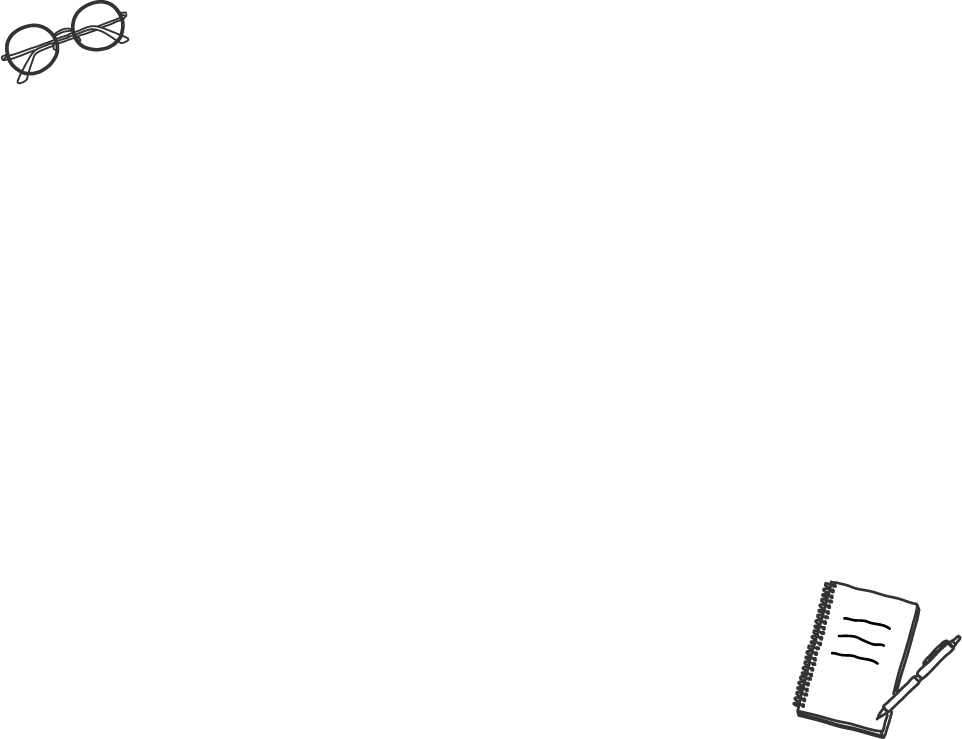

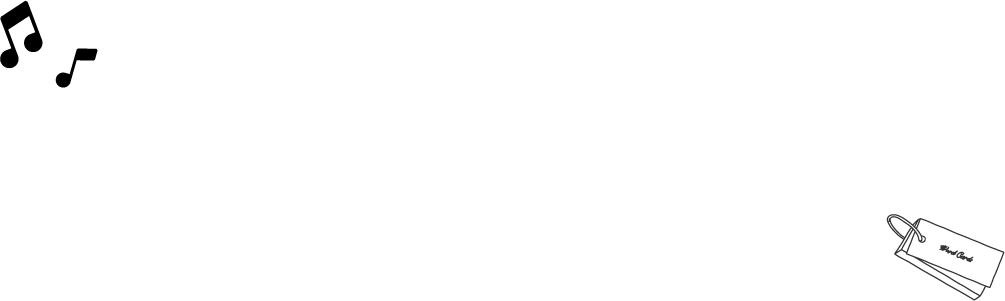
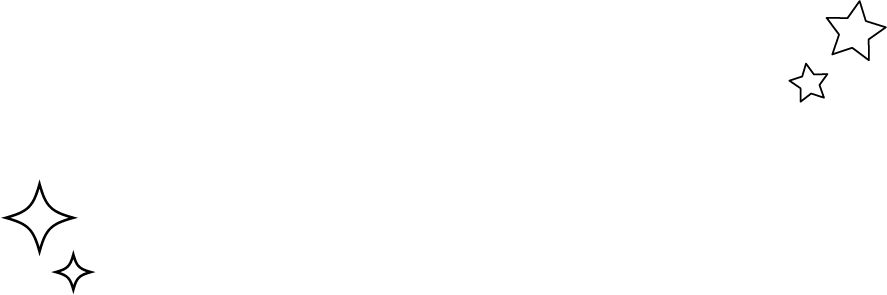
2024年の商学部ゼミファイルVol.1では、商業学科と経営学科の2つのゼミを異なる切り口でご紹介します。1年次の学生は、ゼミナール選びにもぜひお役立てください。
日本大学商学部で
石井ゼミナール
商業学科
石井 美緒教授
ゼミテーマ
電子商取引・情報倫理及び
知的財産法に関する諸問題
学生数
2年生8名/3年生15名/4年生8名
身近な事例から法制度を学ぶ
インターネット取引に関する法律問題や知的財産法、情報倫理などを中心とする法制度を研究しています。時事問題を題材に、現行制度の分析や社会における新たなルール構築の適否等を検討しながら、多面的に考える力や論理的思考力、法的思考力を培います。また、外部の専門家の講義や裁判傍聴等の体験も大切にしています。
石井ゼミを知る つのキーワード
つのキーワード
#01具体と抽象
ゼミでは、裁判例や新聞報道等の事例(具体)を基に対立する利益を考え、その利益を調整する社会のルール(抽象)を検討したり、あるいは既存の法制度から逆に利益調整を分析したりするなどしながら、論理的思考力を養うことを重視しています。
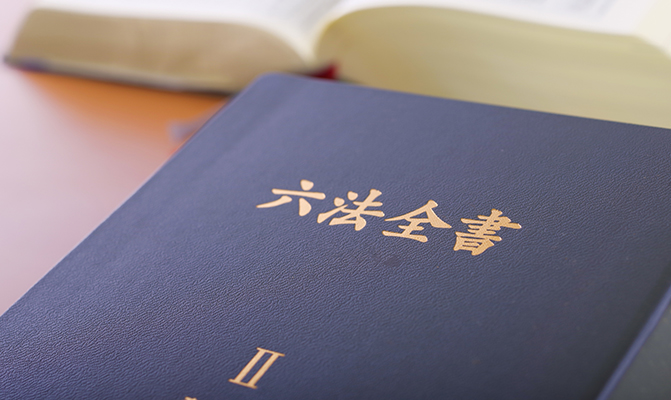
#02多様な意見の尊重・可視化
ゼミ生には「当たり前」を疑い、意見や質問をためらわないよう伝えています。そのためにも、ゼミでは、建設的で積極的な対話がしやすい環境づくりを意識しています。また、学生自ら議論の内容を板書し、論点を整理して検討事項を可視化できるようにしています。
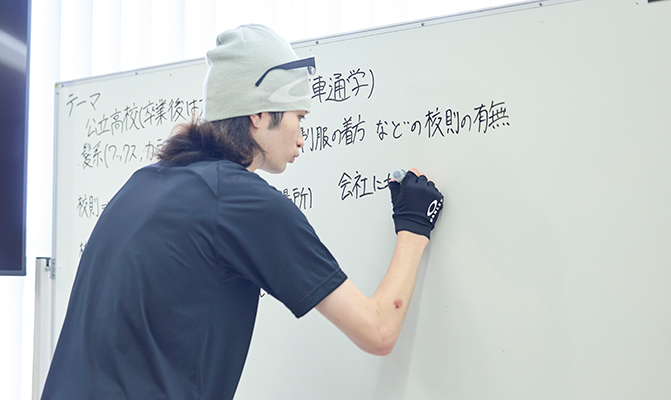
#03学生主体のゼミ運営
石井ゼミでは発表するテーマを学生自身が決めます。そのテーマを深く考察するために最適な手法(ディベート、プレゼンテーション、模擬裁判など)も学生が検討。論点を明確にするために最適な手法は何なのかを考えること自体も、論理的思考力の向上につながると考えております。
ある日の石井ゼミ
活発な意見交換を重視している石井ゼミでは、ディベートもよく行います。
 校則の法的な合理性・相当性を考え、ディベートする
校則の法的な合理性・相当性を考え、ディベートする
日本の公立高校で定められている毛髪や制服等に関するさまざまな校則の事例を列挙し、それぞれについてゼミ生を「違法」と考えるチームと「適法」と考えるチームに無作為で分け、多様な観点から2チームがディベートしました。また最後には、ジャッジ役の学生が説得性などの観点から、公平で客観的な勝敗を判定しました。
 ゼミ生の活動コメント
ゼミ生の活動コメント
多様な校則がある中で、「公立高校の校則は自由であるべきか否か」をテーマにディベートを実施しました。私は自由であるべきではない派として参加。さまざまな校則を具体的に検討しましたが、議論が特に白熱したのがメイクに関してで、「経済的に余裕のある生徒とそうでない生徒との平等性が確保されない」ということが争点になりました。最終的に教育基本法などの主張がジャッジの判断に影響し、校則は自由であるべき派が勝利。ディベートは相手の主張に対し、適切な反論を展開することが重要だと学びました。
石井ゼミ2年生

私たちは「校則の適否」を議題にディベートを行い、私はディベートで想定した校則は必要ないという立場で参加しました。事前準備で、生徒の人権や日本の教育法に関する判例についても調査。得た情報をもとに、論理的で一貫性のある主張を構築し、自分たちの立場を強化しました。私は憲法13条の「幸福追求権」に基づき、生徒の服装の自由が保障されていることや教育目的から見て合理的とは言い難いことを主張し、勝利。今回のディベートを通じて、論理的思考力とリサーチ力の重要性を学びました。
石井ゼミ3年生

石井ゼミの活動いろいろ
中川ゼミナール
経営学科
中川 充教授
ゼミテーマ
ビジネスモデルと組織イノベーション
学生数
2年生14名/3年生14名/4年生5名
企業活動を調査・分析する
競合他社と比較して高い経営成果を上げている企業はどのように価値を生み出し、その価値を顧客に届けているのか、経営戦略や組織マネジメントの観点から考察します。経営に関する知見の修得はもちろんのこと、「ゼミ」自体のマネジメントを通じて、主体性や協働する力など社会で活躍するための基礎力も養います。
中川ゼミを知る つのキーワード
つのキーワード
#01魅力的なゼミ生
本学部には学修への意欲が高く、かつ個性的でクリエイティビティに富んだ学生がたくさんいます。そのなかでも中川ゼミには、熱意を持って誠実に研究に臨む学生が多く集まっていることが一番のアピールポイントです。

#02仕組み化されたゼミ運営
中川ゼミでは、運営、学習、広報、企画渉外などの役割分担があり、上級生を中心に、学生自身が主体的にゼミ運営を行っています。そのため、ゼミ生たちには先輩後輩の垣根を超えた絆があり、楽しく、また切磋琢磨しながら学び合っています。

#03他大学のゼミとの交流
数年にわたって、他大学のゼミナールと合同で、研究発表および討論会を開催しています。チームで協力しながらさまざまな意見を集約し、内容をわかりやすく伝えるために検討を重ねて論文を完成させる経験は、その後の成長の大きな糧にもなります。
中川ゼミの3年間
仲間と助け合い、刺激し合いながら着実に成長していきます。
 経営学科4年
経営学科4年
吉澤 典さん

興味のある経営戦略について学べることと、2・3年生がペアになってゼミ活動をする「メンタリング制度」に惹かれて中川ゼミに入室しました。
 活動概要
活動概要
2年次
前期は3年生と一緒に企業研究を行って、研究手法や情報の集め方など研究の基本を教わり、後期は同級生だけで別の企業研究に取り組みました。他大学との合同討論会もあり、多様な意見に触れることで研究への考察がさらに深まりました。
3年次
2年生とグループをつくってEC事業の研究を実施しました。先輩として後輩をリードしながら、協働する大切さなども学びました。後期のビール業界の研究で、私は成熟した市場が新たな視点やアイデアによって再度成長に転じる、「脱成熟化」という概念に興味を持ちました。
4年次
自分の研究テーマを決め、それぞれがゼミ活動の集大成となる卒業論文の制作に取り組みます。私は「脱成熟化」をテーマに研究を進めています。脱成熟化を成功させている企業を考察し、その理由・手法等を衰退している企業に応用する提案を論文中で行う予定です。
 Pick up
Pick up
中川ゼミは、日本大学図書館商学部分館が主催する「ポスターコンペティション」に毎年参加しています。私のチームは、ビール業界について研究したことをポスターにまとめて発表しました。最優秀賞にあたる学部長賞を受賞したときは、喜びでいっぱいになりました。中川先生からアドバイスをいただきながら、チームで試行錯誤して取り組んだ成果だと思います。
中川ゼミの活動いろいろ
11月号では青木ゼミ、遠藤ゼミを
ご紹介します。





 ゼミナール
ゼミナール

 ゼミナール
ゼミナール





















